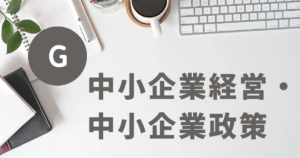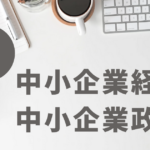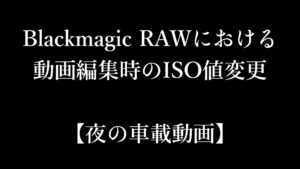中小企業診断士試験の「E.経営法務」科目では、大きく以下のような項目に分かれています。
・会社法
・知的財産法
(特許法/実用新案法/意匠法/商標法/著作権法/不正競争防止法など)
・英文契約書
・民法(民法総則/物権法/債権法/家族法など)
この中で、毎年1問くらい出題されるのが、「英文契約書」問題です。
たったの1問程度しか出題されませんが、対策して対応できるのであれば得点源としたいですよね。
私の勉強方法は、過去問を中心にして、分かりにくい分野が見つかったら、その分野の専門書を読んで、体系的に学んで、理解を深める方法を採用しています。
試験に出ない部分を学ぶこともあり、遠回りかもしれませんが、試験において今後、未知の問題が出る可能性もありますし、なにより、試験に出てくる分野は中小企業診断士として需要がある分野でしょう。
おそらく、中小企業の経営者が困っている分野。
そのため、勉強段階の今に、しっかりと体系的に学ぶことは、まったく無駄ではないと思っています。
今回の記事では、「英文契約書」問題の対策として、私が読んだ本と、その中のオススメ本を紹介したいと思います。
読んだ本は、発行年度の新しい順に並べてます。
- 理由:より新しく発行された本の方が、法律の改訂などに適していると思われるため
ただ、発行年度が新しい方が読みやすい、ということはないため、多少古くて、現在の法律と内容が異なっていても、分かりやすいと思った本は、良い本として判断します。
この場合は、その分野の大筋を理解できたら、発行年度の新しい本にて、改めて内容をアップデートする必要があるでしょう。
私は2025年3月現在、まだ合格していませんが、受験生目線として、本記事が、試験対策本選びとして少しでもお役に立てれば幸いです。
目次
英文契約問題の対策本
- 【2022年11月発行】決定版 英文契約書
- ⭐️⭐️:オススメ(英文が豊富、網羅性が高い)
- 【2020年10月発行】初歩からきちんと英文契約書 第2版
- 【2016年1月発行】はじめての英文契約書の読み方
- ⭐️⭐️⭐️:1番オススメの本!(初心者向け、解説が分かりやすい)
1. 【2022年11月発行】
決定版 英文契約書
【⭐️⭐️】
私が読んだ本の中で、1番発行年度が新しい本が、「決定版 英文契約書」です。
著者について
著者略歴に、「中小企業診断士試験基本委員(2001-現在)」という記載がありました。
調べてみると、令和6年度の試験についても、「基本委員」のようです。
「出題委員」ではないため、直接の関わりはないかもしれませんが、間接的には関わりがあるかもしれません。
英文契約書の問題に関わっているかは分かりませんが、本書が、中小企業診断士試験を解くのに役立つ可能性はゼロではないでしょう。
英文が豊富
英文契約書について、読むことだけでなく、書く場合における注意点なども説明されています。
英文契約書においては、私は以下2つの学習が必要だと思っています。
- よく使われる英単語を覚えること
- 英文契約書に書かれる内容(条項)を知ること(日本語で学習可)
1. よく使われる英単語を覚えられそうか
英文の例文が多く掲載されており、日本語訳もあります。
そのため、よく使われる英単語は何度も触れることができ、自然と覚えていけました。
- confidentiality:秘密保持
- remedy:是正する
- set forth:規定する
- など
ただし、英語学習の本にあるような、
・unit price 単価
・title 所有権
のように、英単語と日本語訳がセットで、英文の下に掲載されているような形式ではありません。
重要な英単語は日本語訳が載っていますが、ほとんどの英単語は載っていないので、
「この英単語は、日本語訳の文章を読むと、この意味だろうな」
というように自分で解釈しないといけないです。
もしくは、辞書などで単語の意味を調べる必要があります。
ただ、冒頭でも書きましたが、同じような英単語が繰り返し出てくるので、自然と覚えていける単語も多いです。
2. 英文契約書に書かれる内容(条項)を知れるか
英文契約書、つまり、日本ではなく海外の取引先と結ぶ契約書において、よく使われる条項を知る必要があると思っています。
これは、英語ではなく、日本語でも学習できると思います。
条項について、日本語でいいので内容を覚えておけば、英単語の意味だけでも分かれば、どのような内容かを予想できるようになり有利でしょう。
- 秘密保持契約っぽい
- 不可抗力の内容っぽい
- など
本書はむしろ、これがメインで、英文契約書で使われる条項が、数多く紹介されています。
まずは英語を無視して、日本語でその内容(条項)を読み進んでいくだけでも、しっかりと中小企業診断士試験の勉強になると思います。
令和6年度(2024年度)の試験問題について
| 「Entire Agreement」:最終性・完全合意 | ◯ |
| 「Force Majeure」:不可抗力 | ◯ |
| 「No Waiver」:放棄の否定 | ◯ |
| 「Severability」:無効規定の分離可能性 | ◯ |
令和6年度の問題(第19問)では、上記4つの用語が出題されていますが、説明ありです。
それぞれの用語の解説を読めば、回答できると思います。
ただ、「No Waiver」の説明はあまり理解できなかったので、オススメ評価を下げました。
各条項の説明については、本記事の3番目に紹介する「はじめての英文契約書の読み方」の方が丁寧です。
2. 【2020年10月発行】
初歩からきちんと英文契約書 第2版
次に、「初歩からきちんと英文契約書 第2版」を紹介します。
結論から言うと、中小企業診断士試験対策にはオススメしません。
中小企業診断士試験対策にはオススメしない
本書は、英文契約書の各条項を説明するというより、どちらかというと、英文契約書の書き方を中心に説明した本です。
以下のようなことが学べます。
- 契約書を結ぶ当事者間で、異なった解釈が生じないようにする書き方
- 自社に不利にならないような書き方
英文を示して、
「こういう書き方だと後で争いになるかもしれないため、こういう書き方にした方がいい」
という説明が多いです。
中小企業診断士試験では、今のところ、「英文の訂正」問題は出ないと思っています。
そのため、本書は、試験対策としてはあまり活用できないと思いました。
ただ、説明が分かりやすく、英文契約書において気をつけるべきことを学ぶことができました。
試験対策でなく、「英文契約書自体について学びたい」と思っている人で、やさしい、入門的な本を探している場合は、本書がいいと思います。
令和6年度(2024年度)の試験問題について
| 「Entire Agreement」:最終性・完全合意 | ◯ |
| 「Force Majeure」:不可抗力 | ◯ |
| 「No Waiver」:放棄の否定 | ◯ |
| 「Severability」:無効規定の分離可能性 | × |
私が見落としていなければ、「Severability」の説明はありませんでした。
そのため、試験対策としての網羅性という点では、本書は少し劣るかと思います。
3. 【2016年1月発行】
はじめての英文契約書の読み方
【⭐️⭐️⭐️:一番オススメの本!】
続いて、「はじめての英文契約書の読み方」という本を紹介します。
2016年発行ということで、2025年現在では少し古めの本です。
ただ、私が読んだ中では、1番のオススメ本です!
解説が丁寧で、読みやすい!
本書は、英文契約書によく出てくる英語表現や、条項について、初心者向けに優しく説明してくれる本です。
英文契約書の条項の日本語訳だけでなく、その条項の意味もしっかりと説明してくれてます。
また、英文の下に、「英単語と日本語訳のセット」が載っているため、英文を訳す力も付きます。
「herein」など、英文契約書によく出てくる英単語についても、しっかり説明がありました。
英文の多さについては、1番目に紹介した「決定版 英文契約書」には劣りますが、解説の読みやすさと、それなりの英文の豊富さにより、一番のオススメの本としました。
令和6年度(2024年度)の試験問題について
| 「Entire Agreement」:最終性・完全合意 | ◯ |
| 「Force Majeure」:不可抗力 | ◯ |
| 「No Waiver」:放棄の否定 | ◯ |
| 「Severability」:無効規定の分離可能性 | ◯ |
上記の通り、令和6年度の試験問題に出てきた用語は、すべて解説されておりました。
「No Waiver」(放棄の否定)について、1番目に紹介した「決定版 英文契約書」では、解説が短く、あまり理解できなかったのですが、本書では、具体的な例も説明されており、理解することができました。
終わりに
私もネットワークエンジニア時代、英文契約書を交わしたことがあります。
海外メーカーのネットワーク製品を自社のサービスで使用できるか検証する際に、特に、秘密保持契約を結ぶことが多かったです。
海外メーカーの担当者は日本人で日本語ですが、外資系企業のためか、基本的に契約書関係は英文が多かった印象です。
長い契約書の時は、日本語バージョンも用意されていたのですが、日本語バージョンにはいつも
「英語版と日本語版で異なる解釈があった場合、英語版を採用する」
のような但し書きが書いていました。
結局、英語版を読まないといけないという状況でした。
秘密保持契約はA4用紙1枚か2枚程度でしたし、どの外資系企業も似たような内容でしたので、一度社内で
「この契約書の内容で締結します」
と承認を得たら、次回以降は、それほど入念に精査せずに、契約を結ぶことができました。
ただ、長い英文契約書や、検証ではなくサービスに使う際の契約書の場合は、上記のようにはいかず、自部署や自社だけで確認するのではなく、自社の契約している弁護士に確認依頼を出したり大変だったのを覚えています。
英文契約書の本を読むと、どの本にも、契約書をきちんと読んで、書いて、契約しないと、
「後から裁判等で問題が大きくなることがある」
と書かれています。
英文契約書に関わらず、日本語の契約書も同様でしょうが、やはり、日本国内ではなく、海外に範囲が広がると、裁判所が変わったりして、不安が大きくなりますね。
中小企業診断士試験で英文契約書が問題に出るということは、英文契約で悩む経営者が存在し、中小企業診断士として助言できるようになることが求められているということでしょう。
本書で紹介した英文契約書の本をしっかり読んで、試験に合格し、中小企業診断士として、少しでも経営者が楽になるように、アドバイスできるようになれればいいなと思ってます。